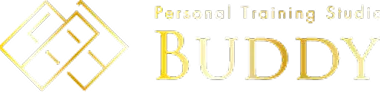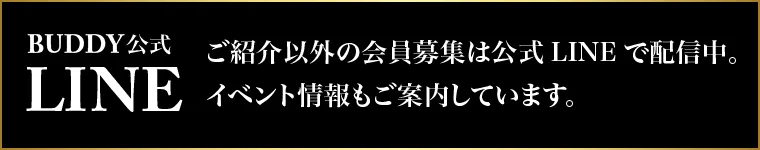目次
こんにちは。
西麻布の Personal Training Studio BUDDY のトレーナー、齋藤くる美です。
今回は、トレーニング効果を最大化するために欠かせない「動作の土台」についてお話しします。
こんな人はいませんか?
週に数回ジムで筋トレ。
ランニングや競技練習も欠かさない。
それなのに、動きが重い。軸が安定しない。フォームが崩れる。腰や膝に違和感が出る。
こうしたケースは珍しくありません。
それは、
筋肉の強さと、体の使い方の良さは別物
だからです。
可動性が乏しく、連動が崩れたまま負荷を上げても、パフォーマンスは伸びず、ケガにつながりやすくなります。
大切なのは、
動く前に、“動ける”身体を整えること。
土台が整うと、技術や筋力がムダなく発揮されます。
パフォーマンスピラミッド
=結果が出る身体づくりの「順序」
スポーツの動きは、急加速・減速・方向転換・回旋など複雑です。
そこで重要になるのが、優先順位の明確化です。
力や技術は、「動ける身体」の上に積み上がるもの。
しかし、その土台となる “身体の使い方の質” が整っていなければ、
どれだけ練習量を増やしても成果は安定しません。
この関係性を示したのが「パフォーマンスピラミッド」です。
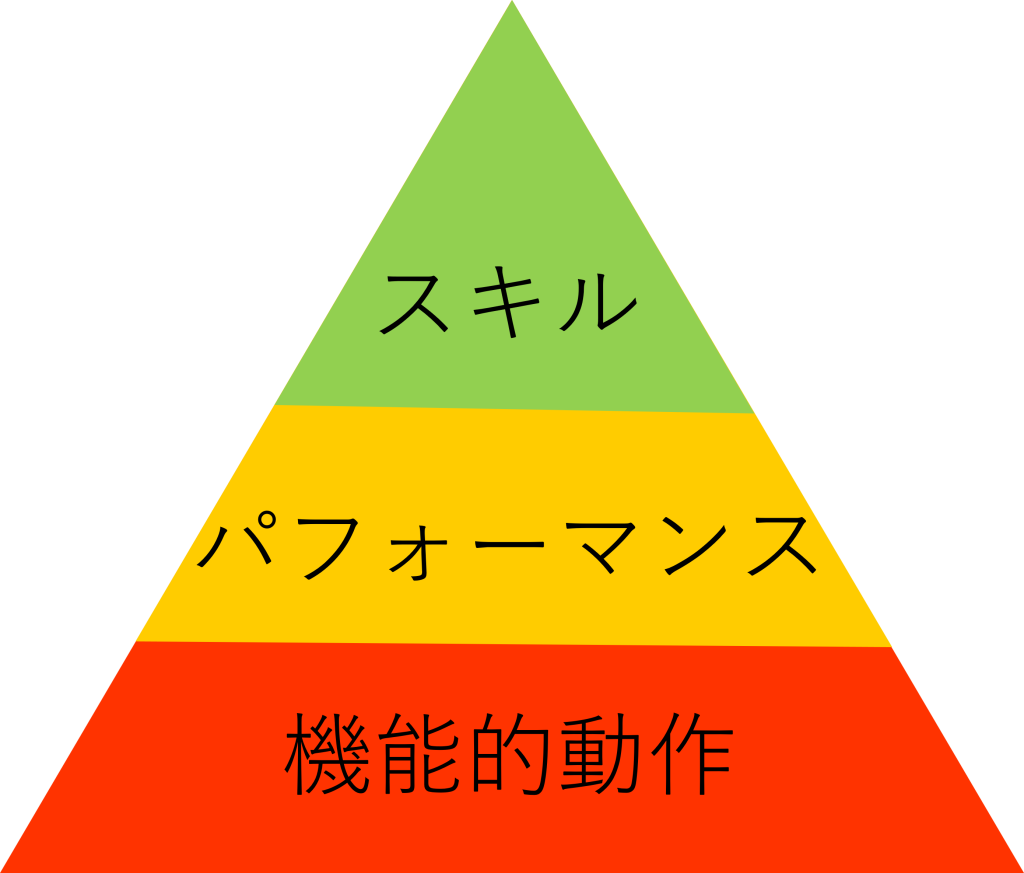
| 階層 | 内容 | 具体的な“できる/できない”の差 |
|---|---|---|
| ①機能的動作(身体操作の土台) | 関節可動性+安定性+姿勢+連動 | ・重心が安定する ・スムーズにしゃがむ/切り替える ・疲れてもフォームが崩れにくい |
| ②パフォーマンス(出力) | 筋力・パワー・スピード・敏捷性 | ・加速/減速が速い ・踏み切りで力が逃げない |
| ③スキル(技術) | 各競技特有の技術 | ・ターン精度が上がる(スキーなど) ・精度が安定し再現性が高い |
多くのアスリートに起きる「順序ミス」
- 出力(筋力)を先に上げる
→ 力はあるのに動きが遅い/怪我が増える- 技術練習ばかりする
→ 癖が固定され、伸びしろが頭打ち- オフでやったことがオンで出ない
→ 土台不足で成果が漏れるこうなる原因は
最下層 =「機能的動作」を整えていないことにあります。
モビリティファースト
= 機能的動作をつくる鍵
機能的動作にはモビリティ(可動性)、スタビリティ(安定性)、プロプリオセプションなどがあります。
このうち、最初に整えるべき要素がモビリティ(可動性)です。
なぜ最初にモビリティなのか?
動くべき関節が十分に動かない状態を放置すると、代償動作という身体は別の関節で動きを補います。
- 力が伝わらない
- 技術が安定しない
- 疲れると崩れる
- 怪我が起きる
見た目は動けていても、本来使うべき場所が全く働いていないことも少なくありません。
そのまま筋トレを行うと、誤った動作だけが強化される結果になります。
モビリティファーストとは?
動くべき関節を動かし、代償のブレーキを外した状態でトレーニングを始めること
そうすることで、
- 力がまっすぐ伝わる
- 連動がスムーズ
- 技術の再現性が高い
- パフォーマンスが伸び続ける
“動ける”身体となり、トレーニング効果が最大化します。
次回の内容(後編の予告)
ここまでが前編です。
次回はさらに深掘り👇
- 関節ごとの役割(ジョイントバイジョイント)
- 分離と協調(動作の統合)
- なぜ怪我を防ぎながら強くなれるのか
後編もぜひご覧ください。
スキーヤー向け短期集中トレーニング実施中
シーズンイン前に集中的にトレーニングをしたい方を限定3名募集しております。
詳しくはこちら👇